特産ラワンブキを育てる JAあしょろ 木村明雄さん一家 |
|
これは大きい。背丈以上のものもざら。それでも今年は生育が遅く、これからさらに伸びて、2.5〜3mにもなるそうだ。 ここにいるとアイヌ民族の伝説にある小人「コロポックル」になった気分。そういえば「コロポックル」とはフキの下の人という意味だと辞書にあった…。 足寄町の螺湾(らわん)地区はその名の通りラワンブキのふるさと。木村明雄さん家族は1.5haの畑でラワンブキを栽培している。 早朝、肉牛の世話を済ませたあと、栄子さんと2人で刈り取り作業。自宅に運んですぐに出荷作業にとりかかる。 木村さんは仲間4人とともに「らわんグリーン研究グループ」を結成、特産のラワンブキを郵便局のゆうパックで全国に発送している。 6月下旬から7月中旬までの1ヶ月で去年は約2400個を発送した。最盛期には螺湾郵便局の2台の集配車では間に合わず、帯広から4トントラックが応援に駆けつけるほどだ。そんなときの出荷作業は家族総出。高校2年の満(みちる)さんも大きな戦力となる。 消費拡大にも力を入れる。マスコミには親切に対応し、テレビ、ラジオ、新聞の取材は数え切れない。栄子さんはグループのメンバーとともに新作料理を研究、フキパイは町の生活改善コンクールで見事大賞を射止めた。 「去年スイスを旅行したらドングリ味のヨーグルトというのがありました。フキのヨーグルト、フキのアイスクリームがあってもいい。それにフキの繊維を入れた紙でお父さんの名刺を作れるのではないかと…」 栄子さんの夢は広がる。明雄さんはラワンブキの畑を今年0.5haほど増やして2haにする計画。昨年は畑作一辺倒から脱却するため和牛の飼育を開始した。肥育と受精卵採取牛育成などに取り組んでいる。 「これからは農業もアイデア勝負。仕事をつくっていけばいいんだ」 と明雄さん。ラワンブキでの成功がそんな積極姿勢を支えているようだった。 |
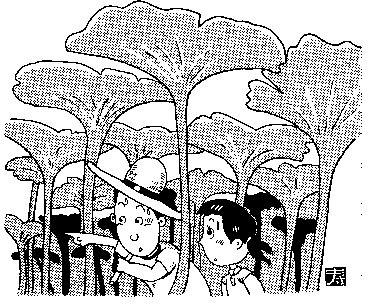
イラスト 石川寿彦氏
採取から畑作へと転換し、 宅配、加工で人気上昇 |
|
足寄町螺湾地区の農家4戸でらわんグリーン研究グループが結成されたのは昭和63年のこと。その前年に十勝管内の特産品を集めた「食のサミット」が足寄町で開催され、ラワンブキを出展したのがきっかけだった。 「塩漬けを真空パックして売ったんですが、こりゃ手間がかかりすぎてダメだと。それで生ブキの一本送りを始めたんです」 グループの代表、木村明雄さんは振り返る。このグループは郵便局のゆうパックでラワンブキを出荷するために結成されたが、グループの名前は発展性を持たせるためにラワンブキの字を抜いた。 平成元年に出荷開始。最初はボール紙の円筒に入れて郵送。ラワンブキ1本を、郵便で送れる最長の90センチに2分割して発送する。しかし円筒のコストが高い。それに10キロ欲しいといった注文もあり、専用の段ボール箱を製作することになった。 「それまで送る箱を探していろいろ苦労しました」 1本送り(約1.8キロ)と10キロ詰め、それに今年から5キロ詰めが加えられ、3種類となっている。 始めて2年目の平成2年には260個をゆうパックで出荷し、道郵政局長から表彰されたほど。しかしその後も出荷数はどんどん増えた。 「自宅で注文を受けたんですが、電話が鳴り止まなくて仕事にならない。郵便局の人に家に居てもらって電話の対応をしてもらったほどです。それで次からチラシには郵便局の電話番号を入れるようにしました」 生産量が増えるに従ってラワンブキの生産現場も野山から畑へと移行した。 ラワンブキはもともと螺湾川流域に自生するフキだが、採り過ぎや河川の氾濫、河川の改修などでその量は激減していた。そこでJAあしょろのバイオ研究所ではラワンブキの増殖を研究、試行錯誤の結果フキノトウから採った種を使って苗をつくることに成功した。 木村さんもその苗でラワンブキの栽培を開始。移植してから3年目で収穫できるが、木村さんの1.5haの畑は立派なラワンブキの「密林」になっている。今年はそこの株を移植し、0.5haほど増やす計画だ。 それに木村さんは去年から和牛の飼育に取り組み始めた。それまでは25haの畑でコムギ、豆類、バレイショ、スイートコーン、その他野菜をつくる畑作専業。複合経営で他から調達していた畑に入れる堆肥も自分で確保できるようになった。 ゆうパックによるラワンブキ送りはグループの5戸の農家合わせて昨年約2400個に達した。螺湾郵便局は廃局の話も出ていたというが、ゆうパックの発送で持ち直し、現在は数人の局員を擁するまでになっている。 「螺湾に住んでいて、ラワンブキを生産できる。ぼくらは恵まれているのかも知れないね」 と木村さんは言う。 しかし単なる地域の珍しい産物だったラワンブキが有名ブランドとしての地位を確立したのは、栽培から発送、新しい料理の研究、マスコミへの対応など、様々な努力があったればこそなのである。 JAの加工事業も軌道に JAあしょろの山菜工場ではラワンブキの一次加工の最盛期を迎えていた。 農家から出荷されてきたフキは一度ゆでてから皮をむき、塩漬けして貯蔵する。次にそれを塩抜きし真空パックや缶詰にして出荷、総生産の8〜9割をラワンブキが占めるほどで、山菜工場はさながらラワンブキ加工場だ。 この工場は昭和48年に足寄町が地域活性化のために建設、1年ほど後にJAあしょろが経営を引き継ぎついだ。 当初は天然のラワンブキのほか、ワラビ、ウド、コゴミなどを加工していたが、原料不足と外国産山菜が極端に安くなったことでフキ以外の地元産山菜の加工は昭和58年をもって中止された。現在はラワンブキのほかは若干の輸入山菜の加工を手がけている。 工場に運び込まれてくるラワンブキもらわんグリーン研究グループ同様、天然物から畑での栽培物に移行しつつある。 今年この工場に出荷している農家は16戸。ラワンブキ栽培の作付け面積は7.5haほど。今後さらに戸数、面積とも増える見込みだ。 塩漬けラワンブキの真空パック、水煮の真空パック、それに1斗缶や丸缶を使った缶詰などを問屋を通して出荷。1斗缶は学校や病院の給食、外食産業、一番小さい0.5キロ入りの缶は贈答用として人気があり生産量を年々増やしている。 しかし工場経営の環境は厳しい。 「フキの皮むきは手作業なのでコストがかかる。農家から買う価格を引き下げることもできませんし、出荷価格をより高くできるわけでもない。どうしても価格のしわ寄せが加工場に来てしまいます」 と桜井熙徳工場長。しかしこの工場があることでラワンブキの生産が農家で拡大していることも事実。なくてはならない存在なのだ。 JAあしょろのラワンブキ生産は螺湾地区のグリーン研究グループと今年から6人増えて18人となったフキ部会(永井庄一部会長)に大別される。部会長の永井さんはラワンブキを2ha栽培していてヤマト運輸の宅急便で全国発送している。 「螺湾のラワンブキがマスコミで取り上げられると山菜工場のラワンブキの売り上げにも良い影響が出る。それに工場の受け入れ量は設備の関係で限度がある」 と桜井工場長。今後生産量が増大すると、さらなる販売努力が必要となってくる。らわんグリーン研究グループなど自ら販売する人々への期待はますます大きくなっているのだ。 ハウス栽培も そのほかJAあしょろでは温泉熱を利用したラワンブキのハウス栽培も最近開始した。町内の安久津政人さんという篤志家が農業振興のために温泉を掘ってみてはと8千万円を寄付。その温泉熱でラワンブキ栽培が100坪のハウス3棟で始まった。 永井庄一さんが生産を請け負っていて2月末から3月末まで「早採りラワンぶき」として足寄郵便局から発送。ほかにこのフキを山菜工場でゆで、帯広のデパートで販売するなど、足寄町でのラワンブキをめぐる動きは広がる一方。螺湾川流域に自生していたラワンブキは今や足寄町全体の重要産品になりつつある。 札幌市場の山菜事情 さて消費地での山菜の流通事情はどうなのだろう。札幌市中央卸売市場の丸果札幌青果(株)で長年山菜を担当している長尾将一課長代理にうかがった。 札幌市場に入荷する山菜といえばヒトピロ(行者ニンニク)とタラノメ、フキ、ウドが4本柱。ヒトピロは野生の物が9割、栽培物が1割、タラノメは野生が7割、栽培が3割、フキは9割が野生、ウドは野生と栽培が半々というのが大まかな割合だ。 ヒトピロは栽培物が1月上旬から出てきて6月10日ごろまで。野生の物は3月10日ごろから6月10日ごろまで出る。タラノメは1月上旬から3月までは栽培物が主力。4月10日ごろから5月10日ごろまでが野生の物。ウドは1月から6月20日ごろまでだが、野生の物が出てくるのは5月5日ごろから6月10日ごろまで。フキは4月上旬から6月20日くらいまでで、主に野生の物を取り扱っている。ラワンブキ系統は当別町の農家1戸と月形町の農家1戸から入ってきている。 山菜は根強い需要がある。このごろは山に入っても思うように採れないのでスーパーの店頭で調達ということが多いようだ。そのため単価は年々高くなって、去年と比べヒトピロで127%、タラノメが113%、フキは横這い、ウドは108%だった。 「タラノメは山から枝の先を切ってきて、芽を出させています。それで山の資源の枯渇が問題になっている。タラノメや野生のヒトピロは資源を残し育てながら採っていくという考え方をしていかないと。山は泣いていますよ。限られた資源だから大切に使わなくてはならないということを強調したい」 と長尾さんは結んだ。 |
家の光北海道版 1996年9月号
良いものを 各地から
