マイタケで「きのこの里」を担う JAあいべつ 安藤徹弥さん一家 |
|
一歩内部に足を踏み入れると…。まさに工場、そんな印象だ。パイプが天井を這い、さまざまな機械が所狭しと並んでいる。実際、土も太陽光線も必要としないというから、本来の農業とはちょっとちがうのかもしれない。 道内最大のキノコの産地、上川管内愛別町。安藤徹弥さんはここでマイタケを栽培している。水田農家の長男として生まれたが、工業の電気科に進み、東京に就職。コンピューターの保守管理の仕事をしていたところに、父親の富男さんから帰って農業を次ぐ話が舞い込んだ。 当時愛別町は「きのこの里」づくりの真っ最中。富男さんも水田一辺倒からの脱却をめざしたが、そのためにはどうしても徹弥さんの力が必要だった。 6年間の東京暮らしを終えて故郷に帰ってきたのが昭和61年。その後旭川のホクレンに勤めていた厚子さんと結婚し、3児の父親となった。マイタケづくりもこれまで順調だ。 キノコ栽培では温度、湿度、炭酸ガス濃度などを調整し人工的に季節をつくる。 「いかにキノコをだますかなんですよ。年に6回季節が回るんです」 と徹弥さん。天然のキノコが一年かけて経験することをボイラーや冷却機を使って2ヶ月でやってのける。 愛別町はマイタケのほかに、圧倒的な全道シェアを誇るエノキダケ、それにシイタケ、シメジ、ナメコと種類も豊富。「きのこの里」そのものだ。毎年秋には「きのこの里フェスティバル」がひらかれ、町民の何倍もの人々がやってくる。 去年で10回目を迎えたこの催しに徹弥さんは第1回から実行委員として参加。これが厚子さんとの交際を深めるきっかけにもなった。また去年にはマイタケ、シメジ、ナメコの生産者を合わせたマシナ部会の部会長にも就任。それだけ周囲の期待は大きなものがある。 キノコ生産は大手企業の参入などで供給が過剰気味。愛別町のキノコ農家を取り巻く情勢も厳しいが、若い着業者も多いという。 まだまだ発展する力がこの「きのこの里」には満ちている。安藤さんファミリーにお会いしてそんな気がした。 |
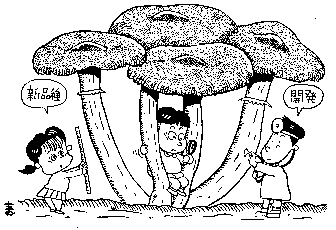
イラスト 石川寿彦氏
個人生産者と企業が対抗 新品種の開発で需要増を期待 |
|
名実ともに「きのこの里」 JAあいべつの平成7年のキノコ類の生産量は約3300トン。道の統計によると全道の生産量は12300トンだから、27%を占めることになる。キノコの種類別の市町村単位の統計でも愛別町はエノキタケとマイタケが第1位、ナメコが2位、シイタケとシメジが4位。名実ともに全道一の「きのこの里」である。 しかしもともとこの町がキノコの名産地だったわけではない。山林はあったものの、水田を中心とした農業が主な産業で、キノコと特に縁があるわけではなかった。 きっかけは昭和45年のコメの生産調整だった。 「1戸平均2町くらいの水田で、補完作物が必要だった。それで気候が似ているキノコの主産地の長野県に町から補助を受けて2人が勉強に行ったんです。その人たちがエノキタケの周年栽培に挑戦して成功し、そのあと『きのこの里』づくりを町や農協がテコ入れし、軌道に乗りました」 JAあいべつの三浦徹きのこ課長が当時を振り返る。キノコの栽培には多額の初期投資が必要。第二次農業構造改善事業や林業構造改善事業で国庫補助が半分、町の補助が4分の1で農家の負担は残りの4分の1だった。町は過疎債を起債して補助に当て、役場とJAにはキノコ専門のスタッフを置いた。 昭和47年に長野県で研修した2人がエノキタケ栽培を開始、2年後の49年からは国や町の補助を受けた施設が次々に建ち、キノコの種類もナメコ、マイタケ、シメジ(ヒラタケ)、シイタケ、ブナシメジと増やしてきた。こうして全道一の「きのこの里」が形づくられていった。 現在のキノコ農家は75戸。生産額は16億円で、コメを中心とした農産物も16億円なら肉牛、豚、鶏卵などを合わせた畜産も同じ16億円。きれいに3本柱が並ぶ構造だ。 キノコ農家は大半が専業化していてその分の農地が水田農家に集約され、規模拡大にも貢献した。さらにキノコ農家は1戸で数人を雇用しており、JAの集出荷施設でも30人ほどが働いている。キノコ関係で300人規模の企業を誘致したのと同じ効果をあげた。 町が起債までしながらJA、組合員が一体となって建設した「きのこの里」がねらい通りの成果をあげたわけだ。しかしキノコ生産者を取り巻く環境はけっして楽ではない。道内でも新たな企業のキノコ生産への参入が相次ぎ供給過剰気味なのだ。 昨年10月に旭川市で開かれたキノコに関するシンポジウムでも、そうしたことが道立林産試験場の伊藤清主任林業専門技術員から発表された。 道内主要十市場に入荷するキノコの道内産の割合は平成6年には82%、ブナシメジを除けば92%に達して飽和状態にあるという。そのため生シイタケ、マイタケを除けばここ数年は低い単価で推移し、特にブナシメジは日持ちがいいなどの理由で生産量を伸ばしてきたが大型栽培者の参入で供給過剰となり、この3年で価格が24%も下落している。 JAあいべつのキノコ生産の推移を表すグラフも、量では伸び悩みながらも右肩上がりを保っているものの、金額では平成5年の18億円をピークに下降した。施設栽培なので電気・燃料代がかさみ人手も不可欠で経費はあまり減らせない。採算的には価格が比較的安定しているシイタケとマイタケを除いて厳しい状況にある。 町内のキノコ生産者を束ねる愛別町きのこ生産組合連合会の西村勝美会長は、積極策で展望を切り開いていくという。 「エノキタケの共同培養センターが稼働すると3割増、ナメコについては倍増の予定です。そうすれば平成10年までに総生産額20億円を達成できる。それに平成8年を販売元年と位置づけ、従来の市場を通した販売のほかに市場外流通などを研究し始めました。PR活動にももっと力を入れていかなくてはならない。それにヒラタケ栽培が消えて5品種になったので、新たな品種を導入し、品数をそろえて文字通りの『きのこの里』にしていく考えです」 培養センターはキノコ栽培の前半を占める菌の培養の行程を集約管理するもの。農家ではその行程がなくなるので今の施設をキノコが発生する行程にだけ使え、大幅な生産増が可能となる。 「愛別のキノコ農家では経営破綻でやめた人はほとんどいない。病気などでやめた人の施設は脱サラなどの新規着業者が継いでいる。みんなが助け合って品質の向上につとめている。量と質の両方をさらに高めることが課題です」 道内ナンバーワンの「きのこの里」は積極策によって先頭を突っ走りリードをさらに広げていく気構えなのだ。 開発力にたける企業 道内では各地で企業によるキノコ栽培への参入が続いている。その代表例が平成7年に生産を始めたホクト産業苫小牧きのこ研究開発センターである。 ブナシメジだけを大量生産し、道内の生産量は急上昇、価格の大幅下落をもたらした。 同社は長野県に本社を置き、もともとはプラスッチック製のビンなどキノコ栽培関連の大手資材メーカー。のちにキノコの新品種開発に乗り出し、さらに自らもキノコ生産者として名乗りを上げ、長野県をはじめ、新潟県や福岡県などに次々と生産施設を進出させている。 苫小牧のセンターは従業員140人で年間3千トン、21億円の売り上げがあるという。JAあいべつに生産量では及ばないものの金額ではしのぐ規模だ。 外観はまさに工場。内部も一つ一つの栽培行程は農家の施設と何ら変わらないものの、栽培している室の大きさは比べものにならず、培養から包装出荷までの行程がすべてラインで結ばれ、合理化、省力化が図られている。そのほかエンジン3機による常時の自家発電設備を備えるなど低コスト化は徹底している。 毎日百グラムのブナシメジが7万2千個、2百グラムのものが1万6千個生産され、道内の主な市場に送り出されている。 名称に研究開発センターとあるように、生産と平行して品種の研究も行われており、そのスタッフが20人。現在はブナシメジの新品種の研究に取り組んでいるという。 生産についても今のところは具体的な計画はないものの、将来の増産は視野に入れているという。 「キノコはこれからのもとだと思います。まだまだ伸びますよ」 と同センターの桐明道典生産課長。愛別町同様にこちらも強気だ。 道内ではそのほか化粧品のカネボウグループが空知の上砂川町の上砂川バイオ(第三セクター)を菌床の供給拠点にしてシイタケ栽培を全道展開、道東の生田原町では地元企業の倉本産業がエノキダケ、ブナシメジなどを栽培していたが新たに遠軽町に大規模なエノキタケの施設を建設した。 愛別町の生産者が増産体制を築くのも、そうした大規模生産施設時代の流れにのっとった対策といえる。農家個々ではとうてい太刀打ちできず、束になるしか道はない。 ほかにキノコ栽培の進む新しい道はないのか。ホクト産業など各企業が力を入れているように新品種の開発が将来発展の一翼を担うことはまちがいない。 その点で北海道は遅れていたことは否めないが、道立林産試験場(旭川市)では平成5年にきのこセンターを開設、品種や栽培方法の開発、普及などに本腰を入れ始めた。 「優良な新品種は開発されているんですがPR不足などもあってなかなか広まらなかった。現在この試験場で開発したえぞ雪の下、エルム・マッシュ、ナラタケの3種類を重点に置いて普及に取り組んでいるところです」 と同試験場きのこ部の富樫巌生産技術科長。普及のテンポは今のところ遅いが、今後も北海道独自のキノコとして広く普及させていく方針だ。 消費拡大はまだまだ可能 キノコを消費者に直接販売している現場から、キノコの将来はどう見えるのだろうか。生協を除けば道内最大の販売額を誇るスーパーのラルズで青果の仕入れを担当する野口英靖さんはこう言う。 「キノコの販売はこのところ年間ふた桁の伸びを見せています。マイタケはテレビで何度も取り上げられたこともあって150%の伸びですよ。昼の『おもいッきりテレビ』など番組で取り上げられると効果がてきめんです。 今後の消費拡大のためには用途の拡大が問題でしょうね。セブンイレブンで弁当、おにぎり、スパゲティのメニューにブナシメジやエノキタケを使い、それを大々的に取り上げて、成功してしています。ハウスのシチューに期間限定でキノコを使った調理法を載せたりしていますが、ほかの商品とのタイアップもこれからますます重要です。大型産地がシェアをある程度確保してから、そうした仕掛けをしていく必要があるんじゃないでしょうか」 キノコ生産が市場で飽和状態にあるという現実がある一方で、価格や用途などの条件が整えばもっと消費が拡大するという見方がある。 企業が大規模生産に乗り出し、農家もコスト削減と規模拡大の選択を迫られているが、やり方によっては消費を増やす可能性は十分。トップ集団を走る愛別町のキノコ生産者や企業には生産の拡大と平行して消費を喚起するためのさらなる努力が求められているともいえそうだ。 道産新品種を道きのこ農協が供給 道立林産試験場で開発されたキノコの3品種は北海道きのこ農業協同組合(三笠市)から種菌が供給されている。 えぞ雪の下は野生のエノキタケに近い品種で、茶系の色が付いており適度なぬめりがあってシャキシャキとした歯ごたえがあり味もよい。 また温度管理なども楽でつくりやすい。ところがエノキタケは現在全体が真っ白な純白系が全盛で、色のついたものは敬遠されるようになり、えぞ雪の下も苦戦しているという。 エルム・マッシュはタモギタケの新品種でダシが良く出て鍋物や天ぷらなど幅広い料理に使えるのが特徴。ニレ(エルム)の木に出るためこの名前がついた。 ナラタケは通称ボリボリで道民に人気の高いキノコ。その人工栽培可能な品種を開発し、栽培や病対策などの技術も十分なレベルに達した。 このほか道きのこ農協で売り出しているユニークなものが室内で栽培できる家庭用のシイタケの菌床。レンガを3つほど重ねたような大きさで3〜4カ月で4〜5回収穫できる。価格は900円。送料は道内が4個まで500円で、1個増えるごとに100円増し。10個以上は無料。 北海道きのこ農協 01267−2−6015 キノコは林産物? キノコ類は統計上は林産物として扱われている。天然のキノコはもちろん、栽培できるキノコも木材腐朽菌といって朽ちた木につくからだ。しかし現実にはホクト産業のブナシメジ栽培では木のおがくずを使っておらず、企業秘密として詳しいことは教えてもらえなかったが農産物を利用しているという。ということはキノコ栽培は林産物から農産物に変化しつつあるということもできよう。 ところでキノコ類の中でも最初から農産物として扱われているのがマッシュルーム。理由は木材腐朽菌ではなく、〃農産品〃の馬糞につくため。もっとも本来マッシュルームは「木の子」ではなく、「〇の子」と呼ぶべきなのかもしれないが…。 |
家の光北海道版 1997年3月号
良いものを 各地から
