初夏を彩る真紅のイチゴ JAぴっぷ町 太田幹雄さん一家 |
|
旭川市の北隣、比布町で水田13ヘクタールをつくる太田幹雄さん・美枝子さん夫婦は今年からハウスイチゴの栽培に乗り出した。 「はじめはまったくイチゴのことを考えていなかったんです。トマトをやってみようと思って友だちに相談したらイチゴの方がいいって言うんで…」(幹雄さん) ホウレンソウやネギはつくっているがイチゴはまったくの素人。しかし栽培技術は先輩たちの長年の努力でほぼ確立されている。特にボイラーを入れた加温栽培が導入されてからは良質のイチゴが長期間収穫でき、収益性がグンと高まった。 自分でもイチゴを生産しているJAぴっぷ町職員の三浦義隆さんは良き相談相手だ。 「長くやっている人より初めての人の方が基本に忠実だから、よりうまくいくようですね」 実際太田さんのハウスでは出荷当初から大粒のイチゴがたくさんとれて滑り出しは好調そのもの。ただしサイズごとにパック詰めする作業は経験を要するらしく「私、選果は得意じゃなんです」(美枝子さん)。 「来年はさらにハウスを増やしたい」と幹雄さん。美枝子さんも「葉物よりイチゴの方が育てるのが楽しい」という。 家族は夫婦と母親、娘二人の五人。民謡という趣味を持ち幹雄さんと2人の娘は全道大会に出場したこともある。そんな明るい家族にイチゴはもう一つ新しいいろどりを添えてくれるにちがいない。 |
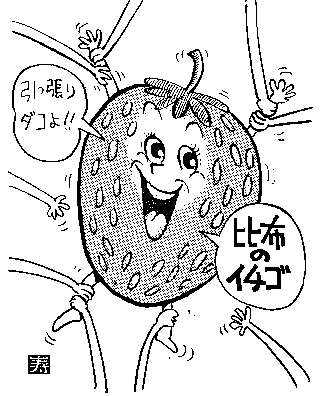
イラスト 石川寿彦氏
『宝交早生』がヒットして ハウス栽培が大幅に伸びる |
|
旭川市の中心部に店を出す銀座渡辺果実店。店頭販売のほか市内のケーキ屋さんの多くをお得意さんに持ち、イチゴの売り上げが商いの半分を占める季節もあるという。まさにイチゴで勝負している果物屋さんである。 JAぴっぷ町のイチゴはすべて生食用。ケーキ屋さんには卸されていない。取材した日もそのイチゴが店頭をにぎわせていた。渡辺優社長(66)の比布産イチゴに対する評価は非常に高い。 「確かに比布のイチゴづくりは上手になってきたと思います。水をやりすぎると柔らかくなってしまうんですよ。きっと指導者がいいんですね」 並べられた比布産イチゴにつけられた値段が1パック600円。卸値が550円で、しかも店では消費税をとらないというから儲けはゼロに等しいはずだ。 「高ければイチゴ離れを起こしますから。650円以上になったら難しいね。でも生産が最盛期になれば値段も落ち着きます。 そのときにはイチゴのスペースがこの倍ぐらいになるんですよ。比布のイチゴが店の売り上げの2割くらいを占めるようになります」 商品の展示の仕方を見ても比布産イチゴがどれほど優遇されているかがわかる。イチゴを商いの中心にすえる銀座渡辺果実店にとって地元産の良質なイチゴはなくてはならない看板商品なのだ。 『宝交早生』導入と「栽培ごよみ」 比布町でのイチゴ生産の歴史は古く大正時代の末までさかのぼるという。もちろん露地栽培でその流れは現在の町の顔にもなっているイチゴの観光農園につながっている。それとは別にハウスイチゴは水田の転作作物として取り組まれた。昭和46年に苗を定植し、47年から生産を開始。3人で始めたものの、出荷したのは2人だけだった。 そのうちの1人でぴっぷいちご部会の部会長をつとめる石原敏幸さん(47)が当時を振り返る。 「10年くらいは手探り状態でした。ハウスイチゴはまったく初めてで何もわからない。農業改良普及所に助けてもらいながら始めました」 稲作仲間の関心も薄かった。 「そのころは減反しても休耕すればお金がもらえた。転作なんてしなくても良かったんです」 始めたものの結果がついてこない。一番のネックは苗。先進地の大野町(渡島)や豊浦町(胆振)に車を走らせ、イチゴ農家で余った苗を買ってくる。 主力だったダナーという品種は冬の長い道北には合わないようだった。休眠期間が長すぎて背丈だけが4、50センチにも伸び、ついた実が15個というように生産性が悪い。病気にも弱いようだった。 昭和49年、現在の宝交早生という品種が農業改良普及員によって豊浦町から持ち込まれる。この導入が好結果をあげ、栽培農家が徐々に増えだした。農協でもイチゴの取り扱いに本腰を入れ始めた。 しかしこの宝交早生というイチゴは身が柔らかくて日持ちがしない。栽培方法やと収穫後の取り扱いを上手にしないと良質で均一な商品として出荷できないデリケートなイチゴだった。そこで昭和54年ごろにイチゴの「栽培ごよみ」を部会が作成、それまで個々バラバラだった肥料の入れ方や管理方法、病害虫防除、収穫方法などの統一を申し合わせた。 その後ハウスイチゴの栽培農家は順調に拡大し生産量も増えていく。平成元年にはハウスイチゴ部会とイチゴ露地部会が合併しぴっぷいちご部会となった。流れは露地からハウスへと完全に移行した。 JAぴっぷ町のハウスイチゴの歴史で宝交早生の導入と「栽培ごよみ」の作成が発展の2大ステップだったとすれば3つめのステップが平成4年からのボイラーを入れた加温栽培。気温の下がる時にボイラーを炊いてハウス内の温度を一定以上に保つ。石原部会長は加温栽培が宝交早生という品種の能力を最も引き出す結果になったという。 「早くて5月10日ごろから収穫していたのがボイラーを入れて3月上旬から出せるようになった。終わりも6月いっぱいもつかどうかだったのが、7月、8月までもとれるようになった。加温が宝交早生という品種の生理に合うことになったわけです」 それまでは収穫が5〜6月の短い期間に集中していたが、そうした極端な山がなくなった。さらにシーズンを通した収量が1.5倍以上に増え、灯油代を差し引いても十分お釣りが来る。いいことずくめである。 ただし初めからからスムーズにいったわけではなく、停電や灯油切れといったトラブルも経験している。 こうして加温栽培が軌道に乗り出すとさらにハウスイチゴへの参加者が増えだした。今年から生産し始めた太田さんもその例である。現在のJAぴっぷ町のイチゴ農家は48戸。生産額は約9千万円で25億のコメ、1億9千万円のホウレンソウに次ぐ額となっている。 太田さんはこの2〜3年で水田を4ヘクタールほど増やして13ヘクタールへと規模を拡大してきた。しかし「イチゴがあれば増やさなかっただろうな」というのが太田さんの今の気持ちなのだ。 コメよりもホウレンソウよりもハウスイチゴは魅力的な作物に成長した。 需要はまだ拡大、夢は水耕栽培へ 平均単価は去年でキロ1100円ほど。300グラム1パックあたり330円程度となる。しかし加温によって出荷時期が早まり、取材時の3月下旬についた値段が1パック550円。生産者も驚く高値である。それでも需要はまだまだあるようだ。欲しいところに行き渡っていないらしい。しかも生産の最盛期の4〜5月になっても需要を全部満たすには至っていないようだ。 じつは比布産ハウスイチゴは旭川市の地方卸売市場にしか出荷されていない。ほかには出回っておらず意外に商圏は小さいのである。ところが需要は大きい。 比布産ハウスイチゴを一手に扱う旭一旭川地方卸売市場(株)果実一課、上田好朗係長(33)はこういうのだ。 「4月、5月のイチゴは宮城、福島あたりから入って来るんですが近年は作付けが減っているんです。暑くなる時期にはつくりたくない、3〜4月で終わらせたいと。この時期は果物の少ない時期なので、スーパーで498(ヨンキュッパ)なら十分売れる。名の通った比布のイチゴということで販売しやすいですからね。いまの3倍、4倍はあっても大丈夫です。6月以降暑くなるとほかの果物が出てきてイチゴの人気は落ちるのですが」 たいへんなモテよう。こうしたラブコールに産地はどう応えていくのか。今後の生産の拡大に向けて石原部会長が課題としているのが新たな苗の供給体制である。 「将来的には水耕栽培で苗が作れればもっと安心できる。新しい品種を探すのも我々の仕事だと思っています」という。 現在は部会の役員が親苗を作っている。その親苗が8月ごろ部会員に渡されて1年間育成。そこからランナーとして飛び出した子どもの苗(原種)を8〜9月ごろ定植し、翌年ようやく収穫となる。 土を使う育苗だとどうしても病気の心配がつきまとう。そこで水耕栽培が考えられるのだ。また宝交早生に代わる品種も模索していかなくてはならない。 20歳そこそこでハウスイチゴに挑戦し、現在の形までリードしてきた石原部会長。増産のための課題は山ほどある。周囲の期待もそれだけ大きいようだった。 |
家の光北海道版 1996年6月号
良いものを 各地から
