越冬キャベツで周年畑作経営 JA和寒町 前鼻彰さん一家 |
|
周囲が白一色の雪原でこの仕事は始まった。まずパワーショベルで雪をすくって穴を掘っていく。1メートルほど掘れば、今度は人間の番。穴に飛び込むと、手で雪の底を探り始めた。ほどなく緑色の球体がゴロゴロ姿を現す。和寒名産、越冬キャベツである。すぐさまこの丸い野菜たちは、手渡しや放り投げのリレーで運搬車に積み込まれていった。 このキャベツは秋に畑で収穫されたあと、そのまま地面に放置される。道北の内陸部に位置する和寒町は降雪が早く、しかも量が多い。当然すぐに雪に埋もれてしまう。しかしキャベツは雪の下でもしっかり生きている。眠ったような状態になってしまうだけだ。雪の中からこのキャベツを掘り出し、ゆっくり暖めてやれば、たちまち目覚め、みずみずしい新鮮なキャベツがよみがえる。 前鼻彰さんはこのキャベツを1.5haつくっている。反収は5トン強なので全部で80トンほど。1日1トン掘り出して80日かかる計算だ。ふだんは智子さんと夫婦2人だけで毎日の作業をこなすが、出荷量を増やすときには家族総出となる。 前鼻さんの畑はなだらかな山を切り開いた開畑でしかも頂上付近。吹きさらしで風が強く、雪は真横から降りつける。 「すぐ前がまったく見えなくなることもあるんですよ。吹雪いた日に山に行くのはやっぱりいやですね」 と智子さん。それにつらいのは冷え込んだ日。暖かい雪の下から出てきたキャベツはすぐさまガチガチに凍ってしまうそうだ。それでも休むわけにはいかない。雪解けまで出荷し終わらなければならないのだ。 このキャベツは全道の主要卸売市場に運ばれている。しかし価格はこのところ低迷し、経営上のうまみはほとんどない。 「高いときにはいいが、安いときにはやになるよね」 と彰さんは嘆く。でも表情はけっして暗くない。冬でも仕事がある喜び、楽しい家族、それに道産冬野菜の安定供給への使命感などが、心の底からの明るい表情を醸し出しているのかもしれない。 |
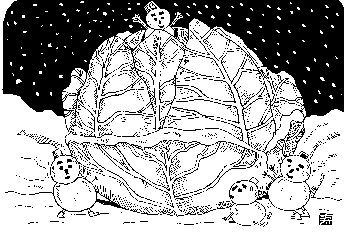
イラスト 石川寿彦氏
価格低迷でも期待の道産キャベツ |
|
越冬キャベツは偶然のたまもの 今から30年ほど前のこと。キャベツをつくってはみたものの、価格が暴落して出荷できないことがあった。やむなく畑に放置していたところ、すぐに雪に埋もれてしまう。ところが翌春、まだ残雪が残るころ、その雪の下には青々としたキャベツが残っていたのだ。 食べてみると、これが秋よりも甘くておいしい。試しに市場へ出荷してみたら、「地場産キャベツがなぜ今ごろ!?」と驚かれ、野菜不足のため高値がついた。 これがJA和寒町の特産品、越冬キャベツ誕生のエピソードである。 昭和45年の水田の減反を契機に越冬キャベツの生産は本格化、47年にはキャベツ生産者が中心となって和寒町蔬菜組合連合会を結成、49〜50年には驚異的な高値をつけ、農家の新築が相次いだという。さらに品種の選定や保存・出荷技術などの研究を積み重ね、安定した生産・供給体制が確立され現在に至っている。 越冬キャベツは農業経営だけでなく家庭生活や地域社会にも好影響を及ぼした。というのは冬の出稼ぎが解消され、家庭や地域が活力を取り戻したからだ。キャベツを雪の下に放置したという偶然が、地域社会を変えることにもなったわけだ。こうしたことが大きく評価され、昨年には第2回ホクレン夢大賞の優秀賞を受賞している。 和寒町蔬菜組合連合会葉菜部会の役員を務める前鼻彰さんは水田9haのほか豆類5.6ha、カボチャ4ha、ビート4haなどをつくっていてキャベツは1.5ha。JA和寒町全体では、降雪前キャベツの出荷が3割で「越冬」は7割だが、前鼻さんは全部「越冬」で出荷している。 雪を掘り出すために中古のユンボ(パワーショベル)を購入、稲作コンバインの走行機能だけを残して荷台を取り付けた自作の運搬車を2台持っている。 前鼻さんはキャベツの作付け面積ではトップクラスで、そうした越冬キャベツ専用の機械を装備しているが、作付け規模や労働力によって作業の方法は様々。排雪は除雪機でキャベツの上の雪をはねのけている人もいるし、スコップを使い人力で済ます人もいる。運搬には自衛隊で使っていた雪上車を改造、荷台をつけて使っている人も多いそうだ。 雪の下から掘り出されたキャベツは空中ですぐにしばれるため、解凍する場所が必要。これにはカボチャの倉庫が使われている。 カボチャは外皮を硬くしたり、内部を熟成させるため一定期間農家で保存(キュアリング)するが、しばれは大敵。そのため断熱材を入れた倉庫を農家個人で持っていて、年内にカボチャをすべて出荷したあとキャベツが入ってくる。JA和寒町のもう一つの名産であるカボチャと越冬キャベツはこうした関連を持っている。 「貯蔵性をよくするため満度ではなく八分の時期に収穫している。傷めないように秋には極力圃場からキャベツを動かさないなど、部会で取り決めています」 と葉菜部会の阿部幸雄部会長。こうした品質保持の努力が市場の高い評価に結びついている。 JA和寒町のキャベツ全体の作付け面積は約85ha。一時は作付けが110ha以上まで増えたが、その後減り気味だ。特にここ2年ほどは価格が低迷し野菜価格安定資金からの給付金を受けている。品質イコール価格にならないところが市場原理の厳しさ。生産意欲も減退気味で、越冬キャベツに頼らず、冬場はほかに働きに出る人が最近増えているのも現実だ。 しかしJAでは弱い相場とは逆に積極策に出る構えを見せている。 「百町歩、2億7千〜3億円が目標。夏にもっと早く出せるようにして、和寒町のキャベツの空白期間を少しでも埋めていきたい」 とJA和寒町特産課の森田晴章課長。大量安定供給で市場をリードする戦略だ。 当別でも越冬キャベツ 越冬キャベツは和寒町で生まれたが、その後隣の剣淵町でもつくられ、ほかにも生産地がある。ただし初冬に早く雪がつもることが条件で、キャベツの大産地、南空知のJAなんぽろでも越冬キャベツを試してみたが、うまくいかなかったという。 ところが札幌市の隣の当別町では小規模ながら越冬キャベツを出荷しているのだ。ただし雪中ではなく、倉庫内に貯蔵する。 1月下旬、JA西当別の共選場の予冷庫内では男女の楽しげな声が響いていた。6戸でつくる西当別キャベツ研究会の人々で、毎日共選作業に精を出している。 この研究会の歴史は浅く、昭和56年に青年部でキャベツを作り始めたのが発端。59年に研究会となり同時に共選も開始した。秋に収穫したキャベツはコンテナに詰められ、野菜の集出荷が終わって閑散となったJAの共選場内に運び込まれ貯蔵される。特にしばれる時にはシートで覆うなど気を使うが、ほかに特別なことをやっているわけではないという。 しばれたキャベツは出荷前に野菜の予冷庫に入れて解凍する。そして部会員たちが選別・袋詰めし主に札幌中央市場へ出荷している。 作付け面積は6戸で2ha、70トンほど。1日4〜5トンを出荷。共選作業は時給制で800円と決めているそうだ。市場価格が安くとも共選の労賃はもらえるが、共選費用・運賃などを引かれた作物本来の手取りは低くなる。 「キャベツばかりで考えればつらい面があるが、こうしてみんなで仕事をすることに意味があるんですよ」 と会長の森本茂さん。当別町は札幌のベッドタウンとして人口が急増。小学校は数年前まで120人だったが、今では600人にもなっている。研究会のメンバーはPTAの会長、副会長などを務めたり、綱引き、ミニバレーなど地域活動のリーダー的役割を担っている。そうした活動の情報交換、お互いが教育し合う場として、この共選作業は欠かせないという。 倉庫も計量のはかりもJAのもので設備費はかかっていない。 「包丁一本で仕事ができる。板前みたいなもんだね。でも安いとついつい一服の方が長くなるよな」 西当別のキャベツ農家はあくまで陽気そのものなのだ。 最大産地の伊達では3分の1を関東のスーパーに キャベツの全道一の産地といえば伊達市。JA伊達市の生産者は127人で作付け面積は約150ha。110ha前後の2位以下に大きく水をあけている。 主力品種はサワー系の北ひかりでおよそ100ha。タキイの種だが、もともとJA伊達市で栽培するために生まれた品種で、北ひかりという名前もこのJAでつけられたという。ほかにボール系や越冬キャベツのような寒玉を合わせて40〜50haといったところだ。 JA伊達市のキャベツ販売で特徴的なのは相対取引が多いこと。北ひかりの3分の1は東京の荷受業者を通してカスミという関東地方の有力スーパーに送っている。道内でも荷受業者を通して特定の加工業者などに供給、最低価格を保証してもらうので、最近のような相場の弱いときには威力を発揮する。そのかわり契約に合わせた農家の生産・出荷体制を確実につくり上げることが大前提。播種・定植の時期をJAで細かく指定し、播種の数日前にならないと種を農家に配らないほどの徹底ぶりだ。 「相対取引は全体の6割になっているが、それ以上にすると危険。契約通り供給できない場合はペナルティをとられるから」 とJA伊達市青果課の瀬林寿行青果係長。全道一の生産はこうして保たれている。 JAなんぽろはJA伊達市に次ぐ全道2位の産地。88人で約120haをつくっている。水田地帯でこれほどキャベツの作付けが増えたのは、気候の好条件だった。南は長沼、千歳方面、北西が江別、当別方面に平地が続いており、その中心に位置していて海からの風が通り抜ける。そのため夏でも風が強く、ムッとするような暑さがない。 まん丸いボール系が主体。出荷は7月上旬から10月いっぱいまで。育苗はJAの施設で行い、キャベツ部会で作付けを調整し、切れ目なく、かつ山を高くしないようにしている。出荷先は道内が六割で、横浜、名古屋、京都、九州など道外が四割。JA伊達市ほどではないが相対取引が多くなっているという。 今後の販売戦略は量の確保と相対取引などの新たな流通だ。 「JA由仁町では25〜30haあり、JA南空知広域連としてロットを拡大していく。それに市場へ出すだけでは金にならないので、売り方を考えていかないと」 とJAなんぽろの原田登美夫蔬菜園芸課長。生産性を高めるために暗きょをめぐらした土地改良なども今後の課題としてあげている。 キャベツは比較的手間のかからない作物で作付け面積も増えてきていたが、ここ3年は市場価格が低迷、採算性が悪化している。その中で大産地は市場外の相対取引などで価格の安定化をはかっているが、相場の主導権はやはり市場流通にある。 そこで大産地はさらに生産を拡大し市場での力を高める方向に向きだした。まさに生き残りをかけた我慢比べ状態で、キャベツ農家の忍耐の日々は簡単には終わりそうにない。 丸果札幌青果 小笠原正利課長の話 平成6年、7年と安かったので8年は大丈夫だという予想で、生産者のみなさんにもそうお話ししたが、結果は回復しなかった。 O157の影響は大きかったと思う。ゆでたり煮たりするほうれん草や小松菜、ブロッコリーは堅調になってきているがキャベツ、レタスが回復していない。 入荷量が減っているにもかかわらず価格が上がらない状態だ。学校給食に使われていないことも大きい。 O157の原因がはっきりすれば消費も回復すると思う。9年度には相場が回復すると予想している。 北海道は将来、日本のキャベツの供給基地に必ずなると思う。輸入物はよほど品薄にならない限り入ってこない。 西洋野菜などいろいろな野菜が出回ってキャベツの需要は横ばいだが、たががキャベツされどキャベツで、今後も野菜の中心を占めることはまちがいない。北海道の生産者に期待しています。 野菜価格安定資金造成事業とは? 北海道農政部畑作園芸課によるとこの事業は指定された産地から消費地に出荷された野菜の価格が著しく低下したときに補給金が出されるもの。 供給安定のための消費者対策という意味が強い。国、道、生産団体が資金を拠出して補給金に当てる。 国の負担が大きいもの、道単独など作物の種類や産地によって負担金の出し方に四つのパターンがある。 補給金の算定の仕方もいろいろあるが、キャベツでは過去の旬別平均価格から1割下がると対象となり、差額の90%〜64%が補てんされる。ただし6割以下に下がっても、それ以下の分は対象にならない。 旬別の平均価格で計算されるため、高値の産地も安値の産地も同様に補給金が出る。高く売れる品物をつくったところほど有利なシステムだ。 平成7年度に道内ではキャベツ、レタス、ハクサイ、ニンジン、ダイコンなど総額で約1億3千万円が補給され、そのうちキャベツは約4千万円を占めた。 |
家の光北海道版 1997年4月号
良いものを 各地から
