道産牛肉の生産拠点をめざす JA上川町 大雪アンガス牧場 |
|
旭川から北見方面へ向かって国道を約1時間、上川町に入ると「ラーメン日本一」とともに「大雪アンガス牛」の看板が目に飛び込んでくる。肉牛はこの町の代表的特産品なのだ。 「昭和51年にアンガス牛を導入したので今は代替わりの時期なんですが、組合員の5戸と1法人すべてに若い人がいるんです。そんなことは珍しいんじゃないでしょうか」 農業組合法人大雪アンガス牧場の藤田浩組合長(49)はこと後継者のこととなると顔がほころぶ。 組合員が素牛をつくり、大雪アンガス牧場で肥育されてほぼ全量が生協に出荷されている。この牧場の3人の専従者も若い。場長の小野寺俊英さん(38)は宗谷管内枝幸町の酪農家の生まれ。ここに来て16年になるベテラン。佐藤亮介さん(28)は埼玉県出身。東京電力の設計の仕事をしていて、3年前にこの牧場に就職した。楠本信彦さん(21)は地元上川町出身だが本州で働き2年半前にUターンした。 「何をやるにもぼくらは考え過ぎちゃうところがあるけれど、若い人は行動力があるからね」 輸入自由化で食料生産の中でも最も厳しい環境にある肉牛だが、大雪アンガス牛の生産現場では、若いパワーと柔軟な発想が新たな道を切り開いていく、そんな予感がした。 |
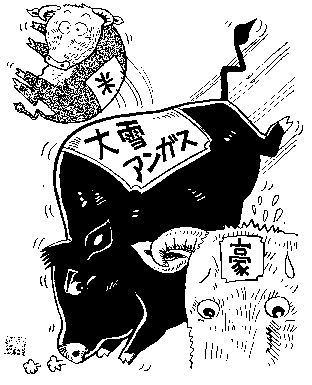
イラスト 石川寿彦氏
品質と安全性をアピールし 低価格の外国産に対抗 |
|
『大雪山の大自然が育てたアンガス牛。本物の味をご賞味ください』 札幌市南区のショッピングセンターSocia(ソシア)。市民生協コープさっぽろのこの大型店にパック詰めされた大雪アンガス牛は並べられていた。 しかしそのすぐ横には「生協オージービーフ」が置かれ『オーストラリアCO−OPヤーラン牧場から安心直送』のコピー。さらに背後の売場では「アメリカンフェア」と銘打ってアメリカ産牛肉が大量に並べられている。 牛肉コーナーは大雪アンガス牛とオーストラリア産、アメリカ産の三つどもえ、さらには国産和牛も加わっての乱戦模様となっていた。 価格を見ると大雪アンガス牛のロースステーキ用がグラム480円に対してアメリカ産が198円と2倍以上の開き。オーストラリア産のロースは置いていなかったが、それよりずっと高級なヒレがグラム380円。 大雪アンガス牛は外国勢にとうてい太刀打ちできない価格である。それでもアンガス牛は売れている。固定客も多いという。 コープさっぽろとの産直活動 スーパーやデパートなど小売りの業界では道内最高の売り上げを誇るコープさっぽろ。札幌だけでなく各地の生協を合併しその範囲は全道へ及ぶ。この生協が発行する月刊誌「コープファミリー」の今年の1月号に、偶然にも大雪アンガス牛の特集が掲載されていた。 「昭和53年、コープさっぽろは上川町農協と大型繁殖農家の協力で、一環ラインによる『大雪アンガス牛』の産地直送事業をスタートさせました…」 「大雪アンガス牛」は登録商標で、そのアンガスとはアバーディン・アンガス種のこと。原産地はスコットランドで角がなく全身が真っ黒な専用肉牛である。その牛を昭和51年から53年にかけてカナダから910頭導入し、上川町での肉牛生産が始まった。 「アンガス牛は足腰が強くて厳しい自然の中でも生きていける丈夫さがある。育成段階では山の中に放っておいても大丈夫な肉牛専用牛なんです。当時の国産牛肉は和牛とホルスタインの雄の肥育牛の二つが主流でした。それでアンガス牛を導入して大衆牛肉としてみんなに食べてもらうおうと。和牛とホルスタインの中間というねらいで始まりました」(大雪アンガス牧場・藤田組合長) 出荷頭数は54年が295頭。翌年には488頭を出荷、その後も毎年出荷頭数を増やし、現在では900頭台になっている。 コープさっぽろの「コープファミリー」で、生産現場はこう紹介されている。 「この地域の気候は高原性で夏でも冷涼。したがって農耕地としてはあまり適さないとされるこの気候が、実は『大雪アンガス牛』の安全性に重要な役割を果たしているのです。というのは夏になっても気温が高くならないのは害虫にとっては悪環境。害虫が発生しないということは、つまり農薬なしで牧草を育てることができるということになるからです。しかもこの辺りは豊富な水資源にも恵まれていました…」 生協が求めるのは安全性と価格。そのうちの安全性については両者の話し合いで理想的な形を見いだしてきた。 「肥育の配合飼料もホルモン剤など添加物は一切使っていない。自然で健康な牛を素牛から肥育まで一貫生産するということで我々も自信を持っています」(藤田組合長) 実務的な交渉以外でも生産者と生協組合員との交流が盛んになった。毎年9月にはバスを連ねて生協組合員やその家族が大雪アンガス牧場を訪ねてきた。その人数が5〜700人。 最近はバス1〜2台と少なくはなったが、イモ掘りなどを楽しんで帰っていく。大雪アンガス牧場は生協が展開する産直事業のメッカでもある。 自由化で価格は低迷したが 大雪アンガス牛は上川町の特産品としての顔も持ち始めた。町役場が発行している町勢要覧では農業の中でアンガス牛が半分以上のスペースを占めるほど重要視され、さらに観光地としても層雲峡温泉などとともに大雪アンガス牧場が紹介されている。いわば町の看板のひとつなのだ。8月に牧場内で催されるアンガスフェスティバルはバーベキュー食べ放題のほか丸太切りや卵投げといったアトラクションも盛りだくさん。5千人が集まるという町のビッグイベントになっている。 こうして成長してきた大雪アンガス牛の生産現場だが、平成3年の牛肉の輸入自由化で経営環境は暗転する。 同牧場が出荷した肥育牛の枝肉単価を見れば、自由化の影響がはっきり読みとれる。昭和54年の初出荷当初から平成元年まで多少の上下はあるが、おおむね1300円台で推移してきた。ところが2年には1200円台、自由化された3年には1100円台に落ち込む。さらに翌年の4年には1000円台、5年には900円台、そして6年には800円台と坂を転げ落ちるように急落したのである。 産直という体制をとっていてもこうした急落は防げなかったのだろうか。コープさっぽろ畜産部次長の野崎幸雄さん(44)は大雪アンガス牛が置かれている環境についてこう話す。 「これまで産直でパートナーシップを築き、それを大切にしてきました。でもそれだけで組合員の支持を得ることはできなくなったんです。それまでは産直というイメージだけで売れましたが品質と価格に対する見る目は非情に厳しくなっている。すでにうちの扱いは国産牛が20%程度で、あとはオーストラリア、アメリカを主体にした輸入牛肉です。国産牛肉も以前は大雪アンガス牛だけだったんですが、今は和牛も置いている。国産牛と輸入牛の品質も大差なくなって、鮮度がちがう程度だけともいえますからね」 コープさっぽろが扱うオーストラリア牛肉は生協の全国組織、日本生活協同組合連合会が直営する牧場から運ばれてくる。牛肉の産直は何も大雪アンガス牛だけではなくなった。そして枝肉相場は大雪アンガス牛が900円前後なのに対しオーストラリアは何と300円程度だという。これでは勝負にならない。 ただし、だからといってコープさっぽろが大雪アンガス牛を見限るのかといえばそうではない。まったく逆らしく今後への期待は大きいものがあるようだ。 「価格と品質を今後どうしていくかが生きるための道だと思います。和牛の下をいく価格では厳しい。そこいでワンランク上げて、和牛のようなスライス商材で行けるのではないか。それに安心度というのはやはり大きな魅力です。つくっている現場がはっきり見えて管理がしっかりしていることは…」 若い後継者が育っている 当初の大雪アンガス牛は和牛とホルスタイン雄の中間をいく商材として走り出した。しかし輸入自由化がそうした路線を打ち砕き、外国勢の価格と量の圧倒的な攻勢にたじたじとなっている。そこで生き残るには外国勢を真正面から迎え撃つのではなく、さらに高級な和牛の方向をねらえというわけだ。 その辺は生協との情報交換を欠かさない産地側でも十分認識している。肥育の期間を延ばして、和牛の品質に迫ろうという動きが始まった。 大雪アンガス牧場発足当初は赤身肉の出荷を前提としていた。牧場の組合員である繁殖農家は子牛を9ヶ月ほど育て、体重が250キロくらいになった時点ですべて牧場に売却する。その後牧場では10ヶ月程度、生後19ヶ月で500〜550キロになった時点で出荷していた。しかし肉質を和牛に近づけるため、さらに肥育期間を延ばし、現在は生後22ヶ月、600〜650キロまで肥育するようになった。 「採算ラインはぎりぎりのところ。コープさっぽろがほかの国産牛より高く引き取ってくれることと、町やJAの支援で持ちこたえているようなものです。繁殖農家では素牛の生産だけで採算はとれない状態です」と藤田組合長。 組合長自身の経営では畑作を組み合わせ、バレイショ12ha、ビート14ha、大豆3.5ha、ソバ5haをつくっている。ほかの組合員もハウス栽培などいろいろ複合させて経営を維持しており、バレイショ、カボチャなどはコープさっぽろの共同購入品目に加えられ、その取り扱いは年々増加している。肉牛生産で吐き出される堆肥がバレイショなどの有機栽培農作物を産み、そして流通段階でも牛肉で培われた有機的な結びつきによって生協組合員に販売されるといった結果を呼んでいる。 そして最大の強みが若い人々が肉牛農家に残っていること。昨年にはクリエーションスタッフというグループが誕生。大型機械を導入し牧草の収穫を開始した。もちろんその担い手は若い人々である。さらにはそれを発展させた耕耘などの作業も請け負う組織が生まれようとしている。 輸入自由化という厳しい環境の中で、若者たちも農業の道を選んだ。産直という先進的な試みを軌道に乗せた親たちから学ぶものは多かったに違いない。そしてその経験を十分生かした新しい農業の形をつくりだし、苦難を乗り切っていくことだろう。 |
家の光北海道版 1996年7月号
良いものを 各地から
